「起業したいけど、資金ってどれくらい必要?」「最低限いくら用意すればいい?」「銀行から借りるって難しそう…」
起業を考えるとき、誰もがぶつかるのが「資金」の問題です。
結論から言えば、起業資金は業種によって大きく異なりますが、自分のビジネスに合わせた予算設計と調達方法を選べば、無理のないスタートは可能です。
この記事では、必要な資金の目安から、具体的な調達方法、銀行融資のコツまで詳しく解説します。
個人事業主と法人 起業手続きにかかる費用

個人事業主・フリーランスとしての起業にかかる費用
個人で起業する場合、基本的な手続きは「開業届」の提出のみです。
この開業届は無料で提出でき、税金や資本金も必要ありません。手軽にスタートできるのが、個人事業主としての大きな魅力です。

法人設立にかかる費用
一方、法人を設立する場合には、登録免許税や定款認証手数料などの初期費用が発生します。
最低でも10万円程度の費用が必要となります。
また、法人にはいくつかの種類があり、代表的なものとして以下が挙げられます:
| 株式会社 | 登録免許税等の費用約25万円 + 資本金 |
| 合同会社 | 登録免許税等の費用約10万円 + 資本金 |
| 一般社団法人 | 登録免許税等の費用で約11万円 |
| 一般財団法人 | 基本財産300万円以上 + その他登録免許税等の費用で約11万円 |
| NPO法人 | 資本金、登録免許税等の費用は不要 |
会社形態によって設立費用や手続きが異なります。
個人事業主と法人、どちらを選ぶべき?
起業を考える際、「個人事業主として始めるか」「法人を設立するか」で悩む方も多いでしょう。
ここでは法人設立の代表的なメリットを見ていきます。
税制上のメリット
個人事業主は、所得税・住民税・消費税・個人事業税などを支払います。中でも所得税は、売上から経費を差し引いた所得額に対して課税されます。
ただし、個人の場合は経費として認められにくい支出があるうえ、所得が増えるほど税率が上がる「累進課税」のため、節税が難しくなります。
一方、法人の場合には、法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人特別税・消費税・固定資産税などが課税されます。
法人税は所得税に相当しますが、税率は比較的緩やかで、節税の余地が広がります。
このような理由から、年間所得が700万円を超える場合は法人設立を検討する価値があると言われています。
信用力の違い
また、法人は一般的に取引先からの信用度が高いとされています。
個人事業主の場合、企業との契約を断られてしまうケースもありますが、法人であればスムーズに契約できることが多くなります。
特にBtoB(企業間取引)を前提としたビジネスを行う予定がある場合、法人化によってビジネスチャンスが広がる可能性があります。
一方、飲食業などBtoC(一般顧客向け)であれば、個人事業主のままでも大きな問題はないことが多いでしょう。
法人設立のデメリットにも注意
法人設立には多くのメリットがある一方で、個人事業主に比べて注意すべき点もいくつか存在します。以下のようなデメリットも理解した上で検討しましょう。
設立・維持にコストがかかる
法人は設立時に登録免許税や定款認証などで最低10万円以上の初期費用がかかります。
さらに、設立後も法人住民税(赤字でも発生する)や会計・税務処理にかかる顧問料など、継続的なコストが発生します。
手続き・管理が複雑になる
法人になると、税務申告や社会保険の手続き、帳簿の管理など、個人事業主に比べて事務作業が増えます。
とくに決算申告は専門的な知識が必要なため、税理士への依頼がほぼ必須となり、その分のコストと手間も発生します。
会社と個人は別人格
法人化すると、会社と代表者(あなた)は法的に別人格になります。
そのため、たとえ会社の利益が出ていても、個人に給与を支払わなければ生活費として使えないという制約が出てきます。
また、会社名義の口座や契約など、すべてを法人単位で管理する必要があります。
個人事業主と法人で起業資金の面で比べてどちらを選択すべき?
法人化は多くのメリットを持つ一方、維持コストや手続きの煩雑さといったデメリットもあります。
そのため、個人事業主としてスタートし、一定の収益が見込める段階で法人化するという選択肢も有効です。
業種別の目安と最低ライン

飲食業の場合
店舗取得費、内装、設備、原材料費、人件費などがかかり、最低ラインで平均300万〜1,000万円程度。
コロナウィルス以降、テイクアウトの需要の高まりで人気になったキッチンカーは店舗型に比べて費用を抑えることができ、一般的には300万〜500万円程度となっています。
ネットビジネスの場合
在庫を持たないECサイトなら、10万〜50万円程度で始めることも可能。
アフィリエイトや動画配信ビジネスなら数千円、数万円から始めることが可能です。
フリーランスの場合
クラウドワークスなどで案件を受注してフリーで働くフリーランスの場合で、名刺・PC・HP制作など最低限で済ませるなら、10万〜30万円程度でスタート可能。
最低限のラインは?
事業内容や規模によって異なりますが、月商の3ヶ月分程度の運転資金+初期費用を想定するのが一般的です。
起業資金の調達方法6選|あなたに合うのはどれ?

1. 自己資金
もっとも王道で、融資時の信用度アップにもつながる。
貯金だけでは限界がある場合もありますが、定期預金など明らかに目的を持って貯金されている証拠となり得る資金は融資を受ける際の審査で高い好印象を持たれます。
自己資金は次のようなものを利用して準備することができます。
- 貯金
- 生命保険の解約
- 退職金
- 株式・投資信託・不動産等の売却
2.身内に借りる
起業資金の調達方法として、家族や親族など、身内から支援を受けるのも一つの選択肢です。
こうした資金提供は「自己資金」として見なされることが多く、金融機関への信用にもつながります。
ただし、年間110万円を超える支援は「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象になる可能性があるため注意が必要です。
また、たとえ親族間であっても、事前に条件や返済の有無を明確にしておかないと、後々トラブルに発展する恐れがあります。
できる限り、贈与契約書などの書面を交わすなどして、リスクを避ける工夫をしておきましょう。
3. 信用金庫や日本政策金融公庫で借りる
信用金庫や日本政策金融公庫を活用すれば、低金利で資金調達が可能。
審査には「事業計画書(創業計画書)」が必須となります。
日本政策金融公庫は、国の政策に基づき、民間の金融機関では対応が難しい分野をサポートする公的な金融機関です。
特に起業時の資金調達先として広く利用されており、低金利で融資を受けられる点が大きな魅力です。
日本政策金融公庫の融資申し込みの流れ
日本政策金融公庫への融資は、随時申し込みが可能です。基本的な流れは以下の通りです。
- 借入申込書と事業(創業)計画書の作成
- 書類を日本政策金融公庫に提出
- 面談
- 審査
- 入金
4. 補助金・助成金
創業補助金、自治体支援などがあり、返済不要の資金として有力。
申請には「実現可能性のある計画書」が必要。
会社設立後6ヶ月ほどで受けられる補助金制度は下記のようなものがあります。
- IT導入補助金
- 地方自治体の創業補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 小規模事業者持続化補助金
会社設立後1年ほどで申請できる補助金制度は下記のようなものがあります。
- キャリアアップ助成金
- トライアル雇用助成金
- 雇用調整助成金
- 人材開発支援助成金
- 人材確保等支援助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
助成金や補助金の情報は商工会、商工会議所で手に入ります。サイトのチェックをしたり、実際に地域の商工会議所に訪れるなどして、最新情報をチェックしておきましょう。
5. クラウドファンディング
近年、注目を集めている資金調達方法の一つがクラウドファンディングです。
インターネット上で自分の実現したい事業や夢を公開し、多くの個人から少額ずつ資金を募る仕組みで、初期費用を抑えながらスタートできる点が魅力です。
代表的なプラットフォームには、「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」や「Makuake(マクアケ)」などがあり、近年利用者が増加しています。
ただし、クラウドファンディングで資金を集めるには、共感を呼ぶストーリーや、目を引く商品・サービスの特徴が欠かせません。
企画内容が曖昧だったり、魅力に欠ける場合は、労力をかけても資金が集まらない可能性もあるため注意が必要です。
利用を検討する際は、事前のリサーチや戦略設計をしっかり行うことが成功のカギとなります。
6. 投資家・エンジェル資金
資金調達の方法として、投資家から出資を受けるという手段もあります。
たとえば、エンジェル投資家とは、個人の資金を用いてスタートアップの成長を支援する個人投資家のことです。
一方、ベンチャーキャピタル(VC)は、事業会社や投資家から集めた資金をもとに、有望なスタートアップやベンチャー企業に投資する法人のことを指します。
出資による調達は、比較的大きな金額を確保できるうえ、返済の必要がないというメリットがあります。
ただし、出資を受けた投資家が経営に関与するケースもあり、自由な経営判断が制限される可能性がある点には注意が必要です。
将来的に事業売却やIPO(株式上場)を目指す起業であれば、投資家やVCからの出資は有力な選択肢となります。
一方で、そういった出口戦略を想定していない場合は、銀行融資などの安定した資金調達方法を選ぶ方が適していると言えるでしょう。
起業資金を調達するうえで最大のカギは「事業計画書」
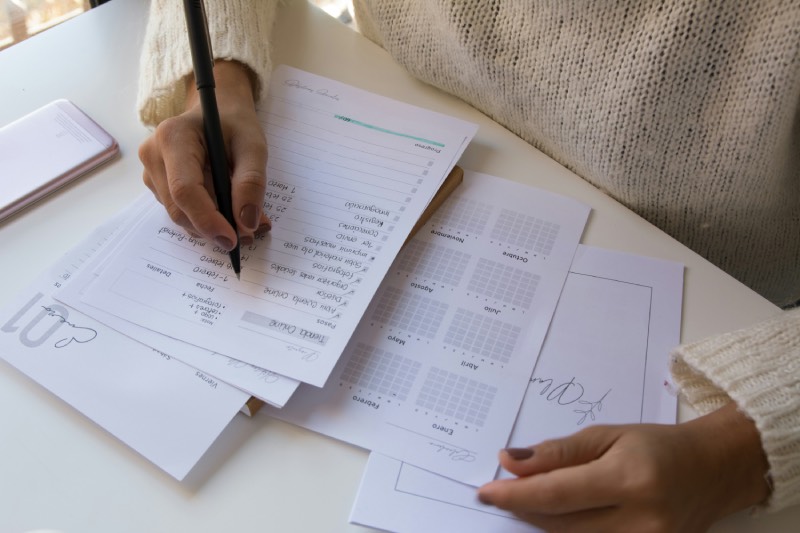
「いろんな調達方法があるのは分かった。でも、そもそも融資とか申請って通るの?」
——そう不安に感じる方も多いはずです。
実は、審査通過率を決める最大の要素は「事業計画書の質」です。
銀行や投資家は、あなたの情熱ではなく、「このビジネスにお金を預けて安心か」を計画書で見ています。
つまり、独学のプランでは通らないケースも多いのが現実。
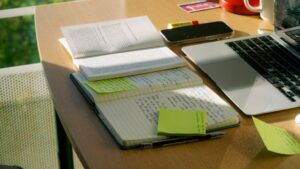
【実績多数】プロが作る事業計画書なら安心!
バルクアップコンサルティング株式会社では、資金調達に特化した「事業計画書作成サポート」を提供しています。
- 銀行融資や補助金採択の実績多数
- ビジネスモデルに合わせたオーダーメイド設計
- 起業初心者にもわかりやすいサポート体制
「何から始めればいいか分からない」方も、無料相談からスタートできます。
\無料相談する/
資金調達向け事業計画書【BulkUp Consulting KK】
起業成功の第一歩は、資金計画のプロに相談することから

起業は人生を変える大きな挑戦です。
だからこそ、「なんとなくの計画」ではなく、プロの視点で整えられた事業計画書が未来を分けます。
資金調達を確実に進めたい方は、ぜひ一度バルクアップコンサルティング株式会社のサービスをご検討ください。
📌 無料相談はこちら|プロがあなたの事業計画を仕上げます!
資金調達向け事業計画書【BulkUp Consulting KK】



コメント